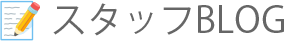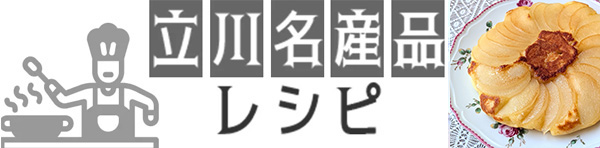立川市内で生産される名産品の数々。育てる方々のインタビュー。
立川で江戸時代から農業を営んでいるという高橋さんの果樹園が今回の名産品レシピの舞台です。先代までは、養蚕や植木を生業にしていたところから、現在代表を務める高橋尚寛さんが、果樹栽培へと踏み出しました。広大な土地のあちこちには、収穫を待つ果樹が整然と並び、最盛期を迎えるところ。高橋さんに、この地で果樹を育てる喜びや栽培の魅力を伺いました!
高橋尚寛さん
立川市柏町で江戸時代から農業を営む十三代目。東京農業株式会社の代表取締役として、先進的な技術に基づいた栽培法を進めている。
立川市柏町で江戸時代から農業を営む十三代目。東京農業株式会社の代表取締役として、先進的な技術に基づいた栽培法を進めている。

甘いものが好き、それが果樹園スタートのきっかけ
立川市は、立川駅を少し離れるとそこかしこに畑が多くあり、作物の成長の様子などから暮らしの中で自然の営みを感じられる地域です。高橋果樹園も立川駅から多摩モノレール砂川七番駅を降りてしばらく歩いたのどかな場所にあります。
取材に伺った8月中旬は、梨の収穫を迎えるところ。まずは、果樹園を始めたきっかけを高橋さんに伺いました。
「父の代は、植木を中心にしていたんですが、私が父の仕事を継ぐというときに、何か食べるものをつくりたいと思ったんです。でも、野菜はあまりピンとこなくて、なら果物だなと。甘いものが好きなので…(笑)。そんなシンプルなきっかけでした。
でも、親の代は植木でしたから、果樹栽培の知識も経験もありません。ですから大学を卒業してすぐ、島根県に研修に行きました。そこで一から果樹栽培の技術を習って、最初に植えたのがブルーベリーでしたね。富士見町にある東京都農林総合研究センターにも伺って、指導していただいたこともありました。約20年前の当時はまだブルーベリーの効能が大々的には言われていませんでしたが、小さくて栄養価が高い果実ということで、徐々に人気が出ていた時期だったので、ブルーベリーは正解でした」
取材に伺った8月中旬は、梨の収穫を迎えるところ。まずは、果樹園を始めたきっかけを高橋さんに伺いました。
「父の代は、植木を中心にしていたんですが、私が父の仕事を継ぐというときに、何か食べるものをつくりたいと思ったんです。でも、野菜はあまりピンとこなくて、なら果物だなと。甘いものが好きなので…(笑)。そんなシンプルなきっかけでした。
でも、親の代は植木でしたから、果樹栽培の知識も経験もありません。ですから大学を卒業してすぐ、島根県に研修に行きました。そこで一から果樹栽培の技術を習って、最初に植えたのがブルーベリーでしたね。富士見町にある東京都農林総合研究センターにも伺って、指導していただいたこともありました。約20年前の当時はまだブルーベリーの効能が大々的には言われていませんでしたが、小さくて栄養価が高い果実ということで、徐々に人気が出ていた時期だったので、ブルーベリーは正解でした」

栽培管理、研究が面白い
今ではブルーベリーの他に、桃、梨、ぶどう、柿、いちじく、キウイなどを主力品目として栽培している高橋果樹園さん。一つの果樹園で7種の果実を育てているところは、実は少ないそうで、一般的には3~4種類が多いのだとか。たくさんの種類を栽培できるというのには、何か理由がありそう。
「これから梨の収穫をするんですが、うちでは根圏制御栽培で育てているんですよ」
梨のエリアに行くと、梨の木が、まるで大きな植木鉢に植えられて並んでいるように見えます。
「これから梨の収穫をするんですが、うちでは根圏制御栽培で育てているんですよ」
梨のエリアに行くと、梨の木が、まるで大きな植木鉢に植えられて並んでいるように見えます。

「これが根圏制御栽培です」
そう言って梨の樹の根元のシートを少し開いて見せてくれました。
そう言って梨の樹の根元のシートを少し開いて見せてくれました。

「梨は土中にある病気の影響を受けやすいので、盛り土をしたところに苗を植え、根の生育を制限するシートを盛り土の周囲に張るんです。そして有機肥料をじわじわと与えながら、24時間水分の管理をしています。この栽培法は生育が早く、また、根の成長が制限されているから木と木の間隔も狭めることができて、土地に対して果樹をたくさん栽培できます。だから果実の収穫量も増やすことができるんです。それに、水分が制限されているので、梨の甘味が増すんです。また、枝をY字型に仕立てることで、葉の日当たり面積を効率よく確保できるんです。手はかかりますが、仕立て方や管理作業によって味わいが変化することは、魅力ですね。こんなふうに土地面積に対して効率よく収穫ができる栽培法にしていることが、たくさんの種類を育てられていることかもしれません」

インタビューの後、梨の収穫だったのですが、このY字仕立ては、収穫しやすいという長所もあるのです。収穫する人の手が届きやすい場所に実がなるので、作業効率もよく、疲れにくいのです。さすがです!
一つひとつ、確認しながら収穫作業は進みます。梨は追熟しないので、完熟の状態を見極めての作業です。
一つひとつ、確認しながら収穫作業は進みます。梨は追熟しないので、完熟の状態を見極めての作業です。
自然相手の仕事だから大変なことは当たり前
ここのところの猛暑で、農作物の被害のニュースを度々聞きます。やはり果樹栽培も大変なのではないでしょうか。
「本当に夏は作業が大変ですね。僕らは暑かったら部屋に入って涼めるけれど、樹は逃げられませんからね。果実の日焼けなどが極力少なくなるように作業しています。あとは、ここのところ獣害も増えています。ハクビシンやタヌキなどが侵入しないようにハウスの周囲に電気の通る柵をはったりしてますが、ハウス栽培していない柿などは、青いうちにカラスやインコに食べられてしまうこともあります。自然相手の仕事ですからある程度は仕方ないですが、これもこまめに手を入れることで最小限になるようにしてますね」
「本当に夏は作業が大変ですね。僕らは暑かったら部屋に入って涼めるけれど、樹は逃げられませんからね。果実の日焼けなどが極力少なくなるように作業しています。あとは、ここのところ獣害も増えています。ハクビシンやタヌキなどが侵入しないようにハウスの周囲に電気の通る柵をはったりしてますが、ハウス栽培していない柿などは、青いうちにカラスやインコに食べられてしまうこともあります。自然相手の仕事ですからある程度は仕方ないですが、これもこまめに手を入れることで最小限になるようにしてますね」
トライ・アンド・エラーを検証して最適解を見つけていく
お話を伺いながら、今度はぶどう棚に移動。ハウスの中は整然と並ぶぶどうの樹と頭上に張り巡らされた枝と葉。あと少しで収穫を迎える大粒のシャインマスカットがたわわに実っていました。圧巻の景色。とにかく、きれいです! 普通はもう少し雑然としているように思うのですが、高橋さんのシャインマスカットの棚は、枝ぶりも葉も等間隔に見えます。

「このシャインマスカットは、1本の枝に1房なるように仕立てています。枝と枝の間隔は30cm。枝につく葉は20~25枚。今は24枚にしているかな。ぶどうは、樹が元気すぎても実に養分がいかなくなるので、葉の枚数を抑えています。こうすることで、ぶどうの実に最大限の栄養がまわり、甘く、大きな実になるんです。けれど時々、枝にもう1房ついて、意外とよさそうに見えるときがあるんです。そうすると、2房いけるんじゃないかなと欲に負けそうになるんですが、過去の経験からやはり実のつく花芽は摘んで、1房に限定する。この作業が大事なんです。せっかくの実をダメにするような気がしてしまうんですが、よい実をつくる大切な作業なので、スタッフにも徹底しています。こうしてその年のシーズンの終わりに、スタッフと一緒によかったこと、悪かったことを洗い出して、次のシーズンに生かすようにミーティングをしています。例えば、枝の間隔が30cmで上手くいったけれど、20cmでもできるのでは?となったら、トライしてみる。その結果、同品質のものができれば正解だし、物足りなければ、また別の正解を見つける努力をする。そんな作業が面白いですね」
お聞きしていると、高橋さんは農家さんでありながら、クリエイティブディレクターみたいな印象を感じます。ぶどう棚自体が高橋果樹園の作品のようで、美しいのです。
お聞きしていると、高橋さんは農家さんでありながら、クリエイティブディレクターみたいな印象を感じます。ぶどう棚自体が高橋果樹園の作品のようで、美しいのです。

東京産の果実のよさを広めたい
高橋果樹園は、東京産ということをメインに発信しています。果樹園では定期的に「摘み取り体験」などのイベントを開催しており、ホームページで募集をすると、あっという間に定員になるほどの人気ぶり。また、取引先は都内のレストランやホテルが主軸。レストランとしても東京産果実というストーリー性が、お客様に喜ばれているといいます。
「おかげさまで取引先にはとても喜ばれていて、また、レストランのオーナーさんも実際にここに来てくれて、納得してくれています。やはり現場を見てもらってなぜおいしくなるのかを知ってもらうと、さらに自信をもってお料理を提供していただけるようですね。東京でこんなにおいしい果実が作れるんだということをもっと広められるように、今後もていねいな栽培管理を続けていきたいと思っています」
果樹園の若き代表として、先端の技術を取り入れながら、指導していただいた先輩からの伝統の技術も大切にしている高橋さん。理性的な語り口の中に、大きな理想が秘められているようで、今後の高橋果樹園さんの展開が楽しみでしかありません! 高橋果樹園さんが、東京の果物の代表的なブランドの一つになるかもしれません!
その高橋果樹園さんの果実が購入できるのは、以下のとおりです。
・直売所…多摩モノレール 砂川七番下車徒歩7分 高橋果樹園 無人販売機にて販売。
直売会は、不定期に開催。詳細はこちらから。
・オンライン販売
「おかげさまで取引先にはとても喜ばれていて、また、レストランのオーナーさんも実際にここに来てくれて、納得してくれています。やはり現場を見てもらってなぜおいしくなるのかを知ってもらうと、さらに自信をもってお料理を提供していただけるようですね。東京でこんなにおいしい果実が作れるんだということをもっと広められるように、今後もていねいな栽培管理を続けていきたいと思っています」
果樹園の若き代表として、先端の技術を取り入れながら、指導していただいた先輩からの伝統の技術も大切にしている高橋さん。理性的な語り口の中に、大きな理想が秘められているようで、今後の高橋果樹園さんの展開が楽しみでしかありません! 高橋果樹園さんが、東京の果物の代表的なブランドの一つになるかもしれません!
その高橋果樹園さんの果実が購入できるのは、以下のとおりです。
・直売所…多摩モノレール 砂川七番下車徒歩7分 高橋果樹園 無人販売機にて販売。
直売会は、不定期に開催。詳細はこちらから。
・オンライン販売